The Better Angels of our nature – why violence has declined
本書について
著者のスティーブン・ピンカーはカナダ生まれのユダヤ人で、現在はハーバード大の心理学の教授を勤めている。サピエンス全史を書いたユヴァル・ノア・ハラリもユダヤ人だが、結構論点が似ているところもあり(暴力の人類史のほうが前に出ている)、特にジェノサイドに対する思いというのはユダヤ人に共通して強く刻まれたものがあるのだろう。
本書では、古代から現代に至るまでに暴力がいかに減少してきたか、また、暴力に関して我々の内なる悪魔がどのように人類の攻撃性を駆り立て、また最近では我々の内なる天使が何を持って暴力行為に走る人々を減らしてきたのか、ということが議論されている。先程紹介した通りピンカーは心理学者だ。なので本当は前半で展開される統計的な事実よりは後半で展開される心理学的な考察の方が本書のメインディッシュなのだと思う。暴力の人類史という物騒な邦題通り本書の中には残酷な人間の歴史が数多く書かれているが、Better Angels of Our Natureという、内なる天使にフォーカスされた英題の通りで、本書は現代の人類が達成した平和な世界を称賛する立場を撮っている。
本書ではトマス・ホッブズの引用が数多く使われている。個人間で振る舞われる暴力については「リヴァイアサン」がとても参考になるようだが、残念ながら私自身は読んだことはない。
われわれは、人間の本性の中に、3つの主要な争いの原因を見出す。第一は競争、第二は不信、第三は誇りである。
ホッブスによればこれらの解決のために人間は暴力を使用する。もちろん、実際には現代ではすべての不和が暴力で解決されるわけではない。むしろ時代を通じて人類は暴力以外の手段で個人間あるいは組織間の不和を解決する方法を見出したり、相手を受け入れる寛容さを育ててきた。
20世紀が「戦争の世紀」と呼ばれていることを振り返ると本当に人類の暴力は減っているのか?ということが疑問に思われるが、実際には戦争による暴力や殺人による死亡は昔の方がずっと多かったようだ。
暴力を減少させた6つの動向
本書の前半では暴力が減った以下の6つの動向について解説される。
-
「平和化のプロセス」:紀元前5000年頃 都市や統治機構を持つ農耕社会の発展
-
「文明化のプロセス」:中世後半 中央集権的な当地と商業の社会基盤
-
「人道主義革命」:17世紀ごろ 社会的に認められた暴力の廃止と平和主義
-
「長い平和」:第二次世界大戦後 超大国、先進国同士の戦争がなくなる
-
「新しい平和」:冷戦終結後 内戦やジェノサイド、独裁政権による弾圧、テロ攻撃の減少
-
「権利革命」:第二次世界大戦後 少数民族、女性、子供、同性愛者、動物の権利擁護
10万人あたりの暴力の死亡率をみると、古代から現代に渡って徐々に暴力による死亡は減っている。上に上げたような要因がこの平和化に一役買っているという。
スコットランドで発掘された氷漬けになった「アイスマン」と呼ばれる古代人が外傷による死亡だったように、戦闘行為は人類には昔からつきものだった。そして暴力による死亡は現代よりも遥かに多かった。しかし文明の発達とともに社会が生まれて国家の中で法の下での暮らしが定着するとこうした暴力は減少した。
また、昔は当たり前のように行われていた拷問や残酷な刑罰も現代では行われることは少なくなった。人権的な観点からは拷問を行うことは国際的な非難の対象になるし、残酷な刑罰をしたところで治安が良くなるわけではないことは社会学的にもわかっている。
第二次世界大戦は大規模な戦争としては最後のものになっているが、その後は先進国同士の大規模な戦争はほとんど起きていない。この理由でよく説明に上がるのは相互確証破壊(MAD)という論理で、核保有国のどちらかが先制攻撃を仕掛けたとしても攻撃を受けた側が報復攻撃を必ず行うという原則だ。相互確証破壊により大規模な戦争は阻止されたという一般的な見方がされることも多い。ただ、本書は核保有が平和をもたらしたという見解についてはやや否定的で、歴史的にも核開発を進めた国はいくつかあったが殆どがその核開発を中断したり核兵器を放棄していたことが紹介される。後の記述でも登場するが、そもそも核兵器による攻撃はほぼタブーのようなものになっており、もはや先進国では使用する方針にはならないだろうと本書は主張する。
国家の内部でおこる内戦やジェノサイドや弾圧も減っているという。日本の近所の国でも国家による弾圧が非常に問題になっているがそれも昔に比べればだいぶ少なくなった。また、従来権力が弱かった少数民族、女性、子供、同性愛者、動物も権利の保護の対象として認められるようになってきたのもこの100年の傾向だ。
暴力による死者が減る過程では、秩序によって、ごくありふれていた暴力が抑制されていった上で、世界にはびこっていた暴力の原因が少しずつ取り除かれていったという印象だ。特に今の平和を促進した因子として、民主主義的な社会や、政府間の組織は大きな役割を担っているようだ。一方で、現在でも暴力が多い地域は貧困地域が多いことが指摘される。
現代に生きる我々は幸福なことに、戦争で死ぬ心配が少ない世の中に生きているわけだが、全く無いわけではない。以前読んだシグナルアンドノイズでも分析されていたが、本書でも、暴力による死亡者数と発生確率についての研究が引用される。この二者はべき乗分布をしているということであり、べき乗分布の特性はファットテール、つまり大量の死亡者数を出すような戦争はあまり起こりそうにはないが起こらないわけではない、ということだ。戦争が起こる確率はランダム事象に近い確率だが紛争が起こる可能性がある限りもしかしたら私達が生きている間にこのような戦争に巻き込まれる確率も無いわけではない。
もちろん私達は危険な世界に生きている、これまで強調してきたように、歴史を統計的に評価すれば、暴力的な大惨事は起こりそうだとは考えられないが、天文学的確率でありえないというわけでもない。これをもっと希望的な形で言い直してみよう。暴力的な大惨事は天文学的確率でありえないわけではないかもしれないーだがそれは起こりそうではないのだ、と。
人間の内なる悪魔と全なる天使
後半の心理学的なセクションでは、暴力を起こしうる人間の内的な要因と、その衝動を止める4つの要因が紹介される。
5つの内なる悪魔とは、まさしくホッブスが述べたような人間の内的な攻撃衝動を担うものだ。
-
捕食的・道具的暴力:何らかの目的達成のための暴力
-
ドミナンス : 名誉欲や集団間の覇権争い
-
リベンジ:仕返しなどの道徳的衝動
-
サディズム:他人の苦しみから快楽を得る
-
イデオロギー:ユートピア構想のなかで善を追求するために無制限に暴力を行使する
これらの悪魔を止める善なる天使は以下の4つとされる。
-
共感:他人と自分の利害を一致させる
-
セルフコントロール:衝動を抑える心の動き
-
道徳感覚:一連の規範やタブー
-
理性:より良い状態になるにはどうすべきかを考えさせる
国家と司法制度、通商、女性化、コスモポリタニズム(理性的な思考ができるようになった)が善なる天使の影響を強くすることに大きく貢献した。
5つの悪魔も絶対的な悪ではない。むしろ普通の人間はこの悪魔に左右されるのはごく自然なことだ。他人から嫌なことをされたらやり返したくなるのは当然だし、嫌な気分のときに苦しんでいる人をみたらスカッとすることだってあるし、食事を得るために他の動物の命を奪う(現代では自ら手を下すことは少ない)のは生きるために必要だ。また、ドミナンスが成長するためのエネルギーに使われたり、理性にコントロールされた崇高なイデオロギーはプラスに働くことも多いようにも思われる。
数多くの心理学的な実験の成果が教えてくれることは、人間は善にも悪魔にもなりうるということだろう。生まれながらに人間に特徴づけられる性質は数多くあるが、学習によって得られる性質も多くある。IQテストが発明されてからというもの、当初はIQ 100が平均だったはずが少しずつテストスコアの平均点は上がっているらしい(フリン効果)。どうやら推論に関する分野の得点が上がっているようで、これは現代の教育の一つの成果ともいえる。推論が表すのは状況から判断して推測する能力で、共感力だったり自分の行動の結果を予測するのには特に役に立つではないかと思う。教育の方針からしても米国の教育は小難しい内容を詰め込むことよりも、原則的なことや論理性を重視していることがこうした事実につながっているのかもしれない。
ボストンの図書館「我が連邦は秩序と自由を守る手段として人民の教育を必要とする」。これを掘った人たちの頭にあった「教育」とは、おそらく、(中略)、読み書きと計算ができて、民主政治と市民社会の背後にある原則が理解できて、指導者とその制作を8日で来て、他の民族と多様な分化を認識できて、そうした理解を皆で共有する教育ある市民からなる国家の一員であると自覚できることだろう。これらの能力は、多少の中小推論を必要とするもので、フリン効果で上昇する能力と重複する。
ゲーム理論を利用した戦争を抑制する原理
本文ではほんの少ししか取り上げられていないが、ゲーム理論によって平和を維持するために必要な条件が考察されていたのは興味深かった。二者の関係においてそれぞれのプレイヤーが協力と戦争を選んだときに、お互いが協力を選べば利益を獲得できるが、攻撃を仕掛けられたらこちらも攻撃しない限り損をする(実際にはお互いが攻撃したら両方損する。)という関係があった場合、協力を選び続けていたらおそらくそのプレイヤーは勝ち残れない。こうした構造が存在してきた場合、戦争のインセンティブが働いてしまう。
|
A:協力 +5 and B: 協力 +5
|
A: 協力 -100 and B: 戦争 +10
|
|
A:戦争 +10 and B: 協力 -100
|
A: 戦争 -50 and B: 戦争 -50
|
ただし、この関係によって得られる利益や損失を調整してやる、つまり協力関係によって得られる利益をブーストして、暴力に訴えるプレイヤーにペナルティを課してやることで戦争のインセンティブを減らすことができるかもしれない。協力によって得られる経済的な利益が魅力的になり、戦争を仕掛けても利益が出なければ自然と協力的になっていく期待が持てる。
逆説的に、協力的にしようとしても大不況で自力で利益を得られなくなり他者から資源を奪わざるを得なくなってしまったことが第二次世界大戦の引き金にもなったのでは、という気もしてしまうが。
経済の問題は暴力と密接に結びついているようにも感じる。第二次世界大戦以降に先進国間での大規模な戦争はなかったとされるが、競争関係はずっと存在しており、その殆どは経済が尺度になっていた。冷戦の終結も結局は経済的な戦争にアメリカが勝ったためにもたらされた。
今、対立が顕在的になっているアメリカと中国にしてもお互いに武力による威嚇は散見されるものの、メインの争いはどちらが世界経済の覇者となるかという点だ。ただ、富を争って命が失われることも多いので経済戦争であっても無血戦争ではない。
国の中の問題としても、紛争まで行かないにせよ経済格差は問題になるし、世の中ではナショナリズムの嵐が吹き荒れているのはどうも経済格差が大きく寄与している。社会主義が失敗したように全員が平等に幸せになる方法なんて無いのかもしれないが、民主主義の枠内で平和裏に人々の不満が解消されることを願うばかりである。
一人の命と百万人の命
ポールスロヴィックが実験での裏付けをとった、スターリンの言葉がある―一人の死は悲劇だが、百万人の子は統計に過ぎない。人は危険にさらされている大量の人間には(あるいは少数であっても)想像を及ぼせないが、名前と顔を持った一人の人間の命を救うためなら喜んで動員されるのである。―
医療機関では「命は金には代えられない」とたった一人の重症患者に無尽蔵に資源が使用されることも多い。全てを保険医療で賄うのは無理だが、資源があって本人の希望があるのであればこのような選択肢ができれば提供できる社会であってほしいと思っている。
一方で文中のスターリンの引用にもあるように、人数が増えてしまうと人の命は統計学的に考えられるようになるというのは医療でもジレンマになっている。臨床試験に参加したが志半ばに亡くなった人はデータの中の一数値として扱われるだけでその人の背景にある人生は関係ない。
戦争になると過去に戦場で亡くなった数多くの人の命は医療機関のようには尊重されなかっただろうと思う。戦争のコマンダー達は大局を制するために個々の生命に思いを馳せることはしないだろうが、できることならば自制心をもって戦争を避けていただき我々の平和な生活を守ってほしいものだ。
終わりに
よく引用に出てくる本でずっと読みたかったのだが、分厚すぎるのと値段が高すぎてなかなか手が出なかったところ、近所の図書館にあるのを見つけて借りてきた。実は英語版が安かったのでゲットしたのだがあまりのボリュームのため2秒で読むのを諦めた。日本語訳されたバージョンでも2冊で1300ページと膨大なボリューム。十分すぎるスペースに濃密な文章が詰め込まれている。


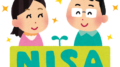

コメント